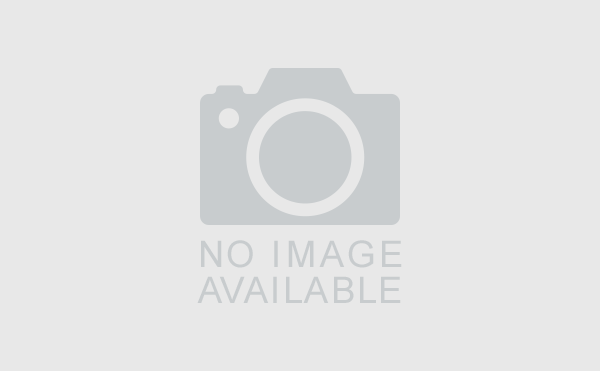第3回 進歩性の審査って、どんな審査?
<公知の発明から容易に創作できたことの論理付けが必要>
特許法には「進歩性」に関する特許要件として、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明することができたときは、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」(特許法第29条第2項)と規定されています。
「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」は、一般に「当業者」と呼ばれている者です。また、「前項各号に掲げる発明」とは出願前に公知になっている発明(以下、「出願前公知発明」と言います。)のことです。「同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」とは、「同項の規定」が「新規性のない発明については特許を受けることができない」(新規性のない発明には特許を受ける権利を認めない)という規定ですので、出願前公知発明に基づいて容易に創作できた発明にも「特許を受ける権利」を認めないという意味です。
新規性の場合は、審査官は、先行技術文献群の中から出願発明と同一の発明が記載された先行技術文献を見つければ、その先行技術文献を証拠書面として出願発明についての特許を受ける権利を否定することができました。
しかしながら、進歩性の場合は、先行技術文献群の中から近似若しくは類似の発明が記載された先行技術文献しか見けられないので、審査官は、それらの先行技術文献を証拠書面として提示しただけでは出願発明の進歩性を否定することはできず、それらの先行技術文献に基づいて当業者が容易に出願発明を創作できたという論理付けまで示す必要があります。
<審査基準に論理付けに関する基準が設けられている>
審査官が出願発明に近似若しくは類似した発明が記載された先行技術文献A,Bを用いて当該出願発明が容易に創作できたという論理付けをするには、例えば、先行技術文献Aに記載の発明(以下、「主引用発明」と言います。)に先行技術文献Bに記載の発明(以下、「副引用発明」と言います。)を適用して出願発明が容易に創作できたという論理付けをする必要があります。
そして、その論理付けには、当業者であれば主引用発明Aに副引例発明Bを適用することが容易であると言える基準(進歩性を否定する方向に働く基準)と、当業者であれば主引用発明Aに副引例発明Bを適用することが容易であると言えない基準(進歩性を肯定する方向に働く基準)を考える必要があります。
そのため、特許庁では「進歩性の審査基準」に、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けについて、下記(1),(2)の基準を設けています。
(1)進歩性が否定される方向に働く動機付け
① 主引用発明と副引用発明に技術分野の関連性がある
② 主引用発明と副引用発明に課題の共通性がある
③ 主引用発明と副引用発明に作用・機能の共通性がある
④ 主引用発明又は副引用発明の内容中に示唆がされている
(2)進歩性が肯定される方向に働く動機付け
⑤ 出願発明に主引用発明及び副引用発明にはない有利な効果がある
⑥ 主引用発明に副引用発明を適用することの阻害要因がある
<進歩性の審査の例>
進歩性の審査基準に、下記の審査例が記載されています。
【請求項に記載の発明(出願発明)】
アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える電話装置。
【主引用発明】
アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える電話装置。
【副引用発明】
アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替えるファクシミリ装置。
出願発明、主引用発明、副引用発明は、それぞれ下記のような構成要件に分説することができます。
【出願出願発明】 構成要件a+構成要件b
a アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える宛先並替手段
b を備えた電話装置
【主引用発明】 構成要件a’+構成要件b
a’ アドレス帳の宛先をユーザが設定した重要度に応じて並べ替える宛先並替手段
b を備えた電話装置
【副引用発明】 構成要件a+構成要件b’
a アドレス帳の宛先を通信頻度に応じて並べ替える宛先並替手段
b’ を備えたファクシミリ装置
主引用発明は、出願発明に対して構成要件aだけが相違しています。副引用発明には構成要件aが記載されていますが、 副引用発明の構成要件bは出願発明と相違しています。
主引用発明の構成要件a′を副引用発明の構成要件aに置き換えば、出願発明が創作できるとの論理付けが考えられますが、その論理付けは当業者が容易に創作できたと言えるものか否かを検討する必要があります。
主引用発明と副引用発明は、構成要件a、bのいずれも相違していますが、構成要件bと構成要件b′はいずれも通信装置に該当し、技術分野は共通しています。構成要件aと構成要件a′は、アドレス帳の宛先を並べ替える機能において共通し、いずれもユーザの使い勝手を良くする効果を奏します。
そうすると、主引用発明に対して副引用発明は、審査基準の⓵技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用・機能の共通性を充足するので、審査官は、当業者が主引用発明の構成要件a’を副引用発明の構成要件aに置き替えることにより出願発明を容易に創作することができたとの論理付けは妥当(出願発明の進歩性は否定されるべき)であると判断することができます。
なお、特許庁が作成した審査基準に基づく審査官の進歩性否定の判断は、常に正しいというものではありません。審査基準は特許庁の内規に過ぎませんので、審査官の進歩性否定の判断における上記の①~④の基準の適用の仕方に対して出願人は反論をすることができます。